2025年NHK大河ドラマ「べらぼう」の第35話(9月14日放送)ネタバレ&あらすじを読みやすい吹き出し形式で記載します!
 蔦重
蔦重どう展開していくかな
べらぼう全話を吹き出し形式で読みやすくご紹介しています!
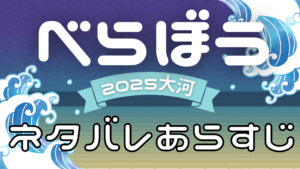
べらぼう35話のネタバレとあらすじを吹き出しで解説:定信の感動
年が明けてしばらく経った頃、定得の腹心・水野為長が市中の本屋から新刊の黄表紙を買い集めてきた。
今年、売り出された本にございます
差し出された本の山から、定信は一番上に置いてある本を手に取った。
蔦屋が出した、誠堂喜三二作『文武二道万石通』という黄表紙だ。
舞台は鎌倉時代。
主君・源頼朝に請われ、忠臣の畠山重忠が鎌倉武士を文に秀でた者、武に秀でた者、そしてどうにもならないぬらくらにより分けるという内容である。
ちなみに「万石通」は玄米と拠を選別する道具のことだ。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)水野、これはもしや
本を開いた定信が、重忠の絵を指し示した。
その声も指先も震えている。
梅鉢!あいや、殿にございますか!
重忠の襟には、松平家の家紋である梅鉄紋がはっきりと描かれている。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)喜三二の神が私を穿ってくださったのか。しかも重忠になぞらえ!
重忠は知恵者の忠臣。殿にお似合いにございますな!
一方、締め上げられる「ぬらくら武士」どもは意次や土山ら田沼一派の者になぞらえられ、しまいには頼朝に擬した将軍・家斉から
文とも武っとも言ってみろ!
すなわち
うんとかすんとか言ってみろ!
と洒落で説教されるというオチである。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)なんとありがたきことだ。昨年は本多らの先走りを許し、赤良の神を責めさせる愚を犯したというに。かように描いてくださるとは
定信は感のあまり目を潤ませている。
しかし、とりようによっては殿が心血を注いでやっている政を馬鹿にしておるとは言えませぬか
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)黄表紙であるのだから面白くはせねばなるまい。肝要なるは蔦重大明神がそれがしを励ましてくれておるということ!
己に心酔している定信は、すべて自分の良いように解釈する。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)大明神は私がぬらくら武士どもを鍛え直し、田沼満に影された世を見事立て直すことをお望みだ!
すっかり自分に酔いしれた定信は断固として言った。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)天明八年腐中、私はいつそう前まねばならぬ!
やる気満々の定信は、さっそく家斉に献言した。
風波蜂須賀家で儒者を務めておりました者を此度、将軍家のお抱えとしてはいかがかと
定信の傍らに控えている柔和な目をした年配者。
阿波徳島藩主に仕える朱子学者の柴野栗山である。
面を上げよ
栗山が顔を上げ、家斉ではなく、将軍のそばに寄り添っている治済をじっと見つめる。
まるで邪悪な気でも感じているかのようだ。
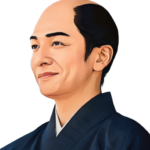 一橋 治済(家治のいとこ)
一橋 治済(家治のいとこ)わしの顔に何かついておるか
治済が不審げに尋ねた。
ご無礼をお許しください。ご尊顔に思わず見惚れてしまいましてございまする
治済は満更でもなさそうに顔を撫で、
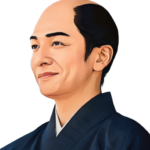 一橋 治済(家治のいとこ)
一橋 治済(家治のいとこ)顔は。うむ、顔はのう
と笑む。
しかし越中、なにゆえこの者を
家斉が定信に問う。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)亡き家治公の治世、栗山先生が上中された『栗山上書』がまこと素晴らしく、此度、田沼病を根本から治すべくお力添えを願った次第にございます
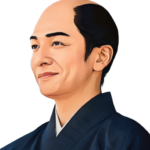 一橋 治済(家治のいとこ)
一橋 治済(家治のいとこ)根本から治すとは何をするのだ
治済の問いには、栗山が答える。
世はしょせん人の集まり。一人一人が正しき人とならねば、正しき世とはなりませぬ。では人を正しき者とするのは何か、それは学問、孔子の教えにございます
続いて定信が、文武奨励のための腹案を自肩に満ち満ちた口調で語る。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)ゆえにまずは世人の範たるべき武家に文武の心得を叩き込もうと考えております。そのために江戸府内に弓術指南所を設け、湯島聖堂も改築し徳川の学問所といたす所存。私はこの日の本をその根本から叩き直しとう存じます!
皮肉にも、蔦重の黄表紙は定信を勢いづかせる結果となってしまったのであった。
べらぼう35話のネタバレとあらすじを吹き出しで解説:世の流れが変わる?
一方、日本橋の蔦屋には『文武二道万石通』目当ての客がわんさと押しかけていた。
旦那様、お客が一丁先まで並んじまってるんですけど!
みの吉が奥の座敷に顔を出し、蔦重に報告する。
『文武二道万石通』が大売れして製本が間に合わず、職人はもとより、ていや手代、女中、小僧まで駆り出して製本作業をしているのだ。
 蔦重
蔦重よし!もう、持ってけ泥棒!
蔦重は紙の束をそのままみの吉に差し出した。
表紙に題箋はついているものの、まだ綴じられていない状態である。
え!このまま渡しちまうんですか?
 蔦重
蔦重綴じ糸もつけてな!
と糸を放る。
太っ腹ですね!じゃあやっちまいますね!
 蔦重
蔦重おい!ちゃんとお代もらえよ!
え!今、持ってけ泥棒って
 蔦重
蔦重言葉のあやだ!べらぼうめ!
みの吉は紙の束を抱え、急いで店に戻っていった。
 てい
ていしかし、とんでもない売れ行きですね
ていも、まさかここまで反響が大きいとは思ってもみなかったようだ。
 蔦重
蔦重おていさん。ひょっとすると、こりゃ世の流れが一気に変わるんじゃねぇですかねぇ
蔦重は気を良くし、したり顔で予測したのだが…。
べらぼう35話のネタバレとあらすじを吹き出しで解説:ただの絵師
歌麿と次の仕事の打ち合わせを終えたところで、蔦重はため息をついた。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)浮かねぇ顔して。飛ぶように売れてんだろ、黄表紙
 蔦重
蔦重まぁ、売れてはいんだけどよ
たとえば、御家人の客たち。
『文武二道万石通』をパラパラめくり、
田沼の一派というのは、やはりぬらくらであるのだな
あとを任された越中守様はまこと、ご苦労が絶えぬことであろう
というふうに、実は定信をからかっていることがまったく伝わっていないのである。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)俺の狂歌絵本は?
虫をお題に詠んだ南畝らの狂歌に、歌麿が草虫図を添えた『画本虫撰』のことだ。
 蔦重
蔦重そっちは、お前の絵があんまりにも良いもんだからよ
と蔦重はまたも困り顔。
『画本虫撰』を試し読みしていた町方の金持ち客は、
これはもうお城の絵師も真っ青ですな
それがこの値とは。いやあ、倹約令様様ですな!
ってな具合なのだ。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)人ってなぁ、思いがけねぇ取り方をするもんだね
歌麿が妙に感心していると、お使いに出ていたていが風呂敷包みを抱えて戻ってきた。
 てい
てい歌さん、お世話様にございます
と歌麿に会釈しつつ、蔦重に慌ただしく伝える。
 てい
てい旦那様。どうも、ふんどしの守様が「将軍補佐』というものになられたらしいです
 蔦重
蔦重将軍補佐あ? ってなんだいそりゃ
 てい
てい上様がご成人するまで、代わりに政を執り行うそうで、ふんどしの守様はもはや公方様も同じと世間様は言ってました
町では賑々しく定信礼費の読売が売られ、真新しい弓を担いだ侍たちや、学び始めたばかりと思しき『論語』の解釈をたどたどしく語る侍たちを見かけたという。
 てい
てい文武に励む侍も増え、ふんどしの守様の勢いは増すばかりの様子にございます
 蔦重
蔦重ちくしょう、おていさん、ひとつ相談なんだけどよ
手持ち無沙汰になった歌麿は、
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)じゃあ俺やこれで
と絵の道具を持って腰を上げた。
 蔦重
蔦重お!んじゃ悪いけど、それ、よろしく頼むぜ
蔦重は片手をあげ、再びていに向き直る。
話し込んでいる二人を残し、歌麿は店の外に出た。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)…もうホントにただの抱えの絵師だな
独りぐちると、どこか吹っ切れたような表情で歩きだした。
べらぼう35話のネタバレとあらすじを吹き出しで解説:きよとの出会い
その帰り道、突然の雨に降られた歌麿は、雨宿りしようといつぞやの廃寺に駆け込んだ。
すると、一人の女が境内の空き地で洗濯物を取り込んでいる。
干してあった色とりどりの着物は、一度では抱えきれない量だ。
このままでは全部濡れてしまう。
歌麿は絵の道具を軒下に置き、
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)手伝いますぜ、娘さん
と女に走り寄った。
手分けして洗濯物を取り込み軒下に移動すると、女は黙って歌麿に頭を下げた。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)いや、あまり濡れてねぇといいな
女が顔を上げた。
あの時、この廃寺で真っ黒に塗り潰した歌麿の絵を拾い集めてくれた女だ。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)あ・・・・・あの、俺のこと覚えてます?まえにここで絵、拾ってもらって
女が自分の耳を寒ぎ、首を横に振る。
耳が不自由らしい。
歌麿が困っていると、女は胸元から使い古した紙片を取り出した。
「きよ一切二十四文」
と書いてある。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)......あ、洗濯女か
この当時、洗濯を生業としつつ、それだけでは食べていけずに身を売る女性が多くいた。
一切とは線香一本が燃える時間。
二十四文とは、河岸女郎の百文よりも安い。
あの時、きよはお堂で、歌麿がヤスと見誤ったならず者ふうの男を相手にしていたのだろう。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)いや。違う違う。あんたを買いてぇわけじゃなくて。えーとね
と歌麿は帳面と矢立を取り出し、黒く塗り潰した絵と風呂敷包みの絵を描いた。
絵を見たきよがアッという顔になる。
思い出したようだ。そして拳を作り、ボコボコ殴る真似をする。
歌麿が男を殴ったことを言いたいらしい。
歌麿が苦笑いして「そうそう」とうなずくと、きよはパッと笑ったー
子どものような、実に無邪気な笑顔で。無意識に見惚れてしまった歌麿を、きよが不思議そうに見る。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)・・・・・・あ、いや!えと。ちょいときよさんを描かせてもらってもいいかい?
仕草で伝えようとしたが、きよは誤解したようで再び「一切二十四文」の紙を見せてきた。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)だから違うって!
歌麿は笑ってしまった。
洗濯物を丁寧に畳むきよ。
立ち上がって雨を見上げるきよ。
歌麿は、きょのいろんな姿と表情を、さまざまな角度から描いた。
どれくらいの時間が経ったろうか。
ふと帳面から顔を上げると、きょと目が合った。
きよは嬉しそうにニコニコ笑っている。
歌麿もなんとなく心和んで、自然と微笑んでしまう。
気づけば、いつの間にか雨は上がっていた。
べらぼう35話のネタバレとあらすじを吹き出しで解説:作戦会議
黄表紙が逆効果となってしまった蔦重は、戯作者たちを集めて作戦会議を開いた。
次の黄表紙は、もう少し分かりやすくからかおうというのである。
 蔦重
蔦重どうも実のとこ、からかってんだってのが伝わりにくいみたいで。ウチはただふんどしを励ましてるとしか思われてないんですよ
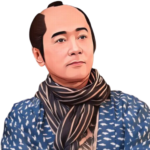 朋誠堂 喜三二 (平沢)
朋誠堂 喜三二 (平沢)ふんどしを落とすつもりが、担ぎ上げちまったってことか
と喜三二。
すかさず三和が
ふんどしのふんどし担ぎか!
と駄洒落を飛ばし、皆が爆笑する。
蔦重も笑ったが、
 蔦重
蔦重って、笑い事っちゃねぇですよ
とすぐ真顔になる。
 蔦重
蔦重このままじゃウチはただの太鼓持ち。いってえ何やってんだかって話でさね
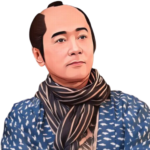 朋誠堂 喜三二 (平沢)
朋誠堂 喜三二 (平沢)次は田沼様を叩くのやめればいいんじゃないの?
と喜三二が茶菓子を食べつつ言う。
 蔦重
蔦重けどそうすっと、露骨にからかうだけになっちまうわけで
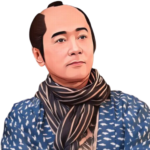 朋誠堂 喜三二 (平沢)
朋誠堂 喜三二 (平沢)そうか。塩梅が難しいねぇ
と自分の「文武二道万石通』をパラパラ。
すると三和が、
あべこべの世相をおかしく並べ立てるってのはどうだい?
と案思を出した。
ご仁政がなって、ありえねえほど幸せな世の中になるって話を描くのさ
政演が
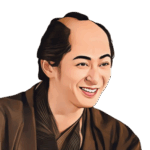 北尾 政演
北尾 政演物乞いまで、緩無着て鯛食ってるとか?
と面白がる。
蔦重はふと、無言の春町が気になった。
春町はじっと手元を見つめ、考え込んでいる様子。
 蔦重
蔦重春町先生、何か言いたいことでも
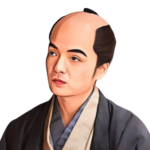 恋川 春町
恋川 春町俺のコレがもっとも売れておらぬというのはまことか?
春町がじっとりした目で見ているそれは、『悦贔屓夷押領』。
絵を北尾政美、自身は執筆に集中し、源義経が生きて北海道に渡ったという伝説を下地に、田沼政権と北方密貿易を材にした作品だ。
こうなった時の春町の面倒くささを知る蔦重、喜三二、政演の三人はヒイッと声にならない声を帰らした。
 蔦重
蔦重ま、まあ、蝦夷は市中にあまり馴染みのないネタだったんで
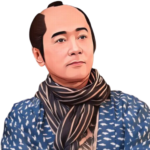 朋誠堂 喜三二 (平沢)
朋誠堂 喜三二 (平沢)そうそう。ネタのせいだよネタの
 蔦重
蔦重誰が描いてもこうなりましたさ
と団結力を発揮して春町をなだめる。
すると、三和が言った。
それによ。先生はある意味一番いい仕事したってことだと思うぜ
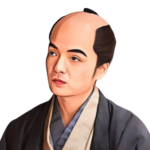 恋川 春町
恋川 春町いい仕事?
だって売れてねぇんだから、先生が一番担がなかったってことだろ!
蔦重たち三人が一丸となって
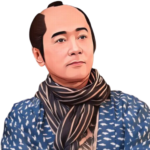 朋誠堂 喜三二 (平沢)
朋誠堂 喜三二 (平沢)そうだ!
そうそう!
 蔦重
蔦重先生が一番!
と言えば言うほど、春町の口角はどんどん下がっていくのであった。
べらぼう35話のネタバレとあらすじを吹き出しで解説:伝わりにくい皮肉
さて、春町の勤務先である駿河小島藩松平家の上屋敷。
四十代半ばの春町は今や藩の重職に就き、今日も対外的な書状などを書いているが、その手が明らかにお留守である。
また案思でも考えておるのか?
耳元で囁かれ、春町は飛び上がった。
当主の松平信影である。春町は慌てて平伏した。
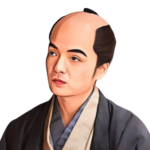 恋川 春町
恋川 春町お役目中に申し訳ございませぬ!
苦しうない、面を上げよ
信義は笑いながら、胸元から春町の『悦贔屓蝦夷押領』を取り出した。
『よろこんぶ』、とびきり面白かったぞ。実に皮肉でな
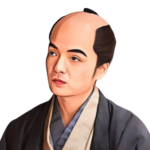 恋川 春町
恋川 春町殿には皮肉をお分かりいただいて
蝦夷の一件は田沼様の一派が必死になってやっておったもの。それを越中守様になぞらえた重忠が田沼様になぞらえた義経に命じてやらせ、押領した蝦夷を頼朝に献上する。蝦夷も押領、手柄も押領、よくお叱りを受けなかったものだ
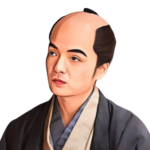 恋川 春町
恋川 春町幸か不幸かその皮肉がまったく伝わっておりませぬようで
伝わりすぎてもお咎めを受けようし、難しいところじゃな
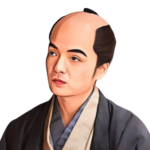 恋川 春町
恋川 春町・・・・・あの、殿は、越中守様の政についてはどのようにお考えで
志はご立派だが、果たして、しかと伝わるものなのか、とは思うかのう
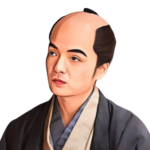 恋川 春町
恋川 春町しかと伝わる?
主君の言った言葉の意味が分かったのは、後日のことである。
べらぼう35話のネタバレとあらすじを吹き出しで解説:ニヤリ
 蔦重
蔦重こないだのあれ、気にしてましたよねぇ、春町先生
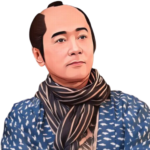 朋誠堂 喜三二 (平沢)
朋誠堂 喜三二 (平沢)どうだろう、まぁ
蔦重と喜三二は、蔦屋の座敷で春町を待っていた。
 蔦重
蔦重こちらから行ったほうがよかないですかね。新しい案思でも持って
蔦重が心配していると、
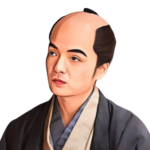 恋川 春町
恋川 春町お心遣い痛み入る
という声と共に春町が入ってきた。
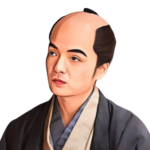 恋川 春町
恋川 春町またへそを曲げておるとでも案じてくださっておるようだが、幸い『よろこんぶ』は我が殿からお褒めにあずかり、俺の中ではもう片がついた
声も表情も明るい。蔦重はホッとした。
 蔦重
蔦重そりゃ何よりで
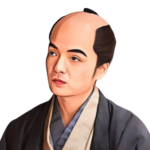 恋川 春町
恋川 春町それより殿が面白いことを仰せであった。俺たちのからかいも通じなかったが、ふんどしの志もまた、そう上手くは伝わらぬのではないかと
 蔦重
蔦重道場への入門は引きも切らねぇ、「『論語』は大売れだって聞きますけども
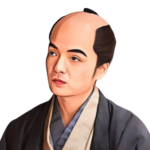 恋川 春町
恋川 春町まさにそこだ。もとから励んでおった者は今さら道場に入門もせぬし、『論語』を買ったりせぬ。つまり今、文武だ文武だと騒いでおるのはにわか仕込みの新参者だ
 蔦重
蔦重新参者
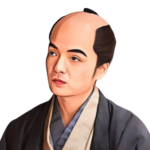 恋川 春町
恋川 春町しかし、文も武も少しかじってその真髄が分かるという類いのものではない。何年何十年もの地道な修養を要するものだ。遠からず皆飽きて、やたら武張ったり知ったかぶりをするトンチキ侍を作り出して終わるのではないかと仰せであった
 蔦重
蔦重トンチキ侍
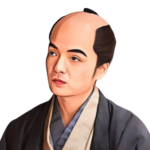 恋川 春町
恋川 春町先ほども店先の品を弓で射っておるトンチキ侍がおった
春町が蔦屋に来る途上でのことだ。
道場帰りと思しき袴姿の侍たちに、瀬戸物屋の主人が「お許しを!」と土下座して謝っている。
そばにいた野次馬に事情を聞いてみると、「礼儀がなってねぇってんで、お武家様に弓の的にされちまったようなんですよ」という無体な話である。
侍たちは「次はお前が的となると思え!」と店の主人を脅しつけ、野次馬たちに「どけ!うぬらも的になりたいか!」と怒鳴りながら引き揚げていった。
春町の話を聞いた喜三二が、煙管の灰をポンと煙草盆に落として言う。
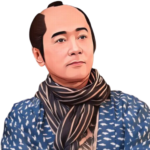 朋誠堂 喜三二 (平沢)
朋誠堂 喜三二 (平沢)そう言えば、こないだ扇屋に顔出したらさ。『馬の稽古だ馬んなれ』って、振袖や女郎にお馬やらせてたのがいたのさ
 蔦重
蔦重振袖や女郎に?
蔦重は耳を疑った。
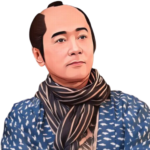 朋誠堂 喜三二 (平沢)
朋誠堂 喜三二 (平沢)弱いモンに威張り散らすのが武家らしいって思ってんじゃないかね
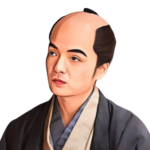 恋川 春町
恋川 春町トンチキよりぬらくらのほうがよほどマシだな
と春町。
 蔦重
蔦重けど、文武に優れた者を作り出そうとしたら、大勢のトンチキが生まれちまったってなぁ、これ以上ねぇ皮肉でさね
春町が
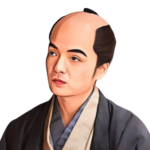 恋川 春町
恋川 春町で、あろう?
とニヤリ。
 蔦重
蔦重へぇ
と蔦重もニヤリ。
傑作が生まれそうな予感がする。
べらぼう35話のネタバレとあらすじを吹き出しで解説:田沼意次との別れ
そこへ南畝が、みの吉に案内されてやってきた。
なんだかやけに表情が硬い。
 蔦重
蔦重おお、南敵先生。どうしました
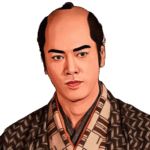 大田 南畝
大田 南畝田沼様が・・・・・・。田沼様がお亡くなりになったらしい
天明八年七月二十四日、田沼意次は塾居のまま江戸で死去。
享年七十であった。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)とうとうくたばったか
江戸城で意次の訃報を受けた定信の第一声である。
田沼の葬列は野次馬が集まりそうだが、いかがすればよいかと奉行所から問い合わせが来ておりますが
訃報を伝えにきた本多忠等が指示を仰ぐと、定信は途中だった市中の報告書に目を戻し、
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)投石を許せ
とさらりと言った。
は?
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)この葬列については、石を投げた者を取り締まらぬこととせよ
本多は
それはあまりに
と控えめに難色を示したが、定信は木で鼻を括ったように言った。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)これ以後、民は恨みつらみをぶつける的をなくすのだ。思う存分投げさせてやれ
その時、まるで抗議するかのように、遠方からゴロゴロと雷の音が聞こえてきた。
松平信明が
負け犬の遠吠えですかの
と意次を蔑み、定信にへつらう。
定信はおもむろに外を見やった。
遠く離れた曇天に一瞬、細い閃光が走る。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)見苦しいぞ、田沼
べらぼう35話のネタバレとあらすじを吹き出しで解説:定信の憂鬱
同じ頃、石燕は家の縁側で絵筆を握っていた。
雷鳴がして空を眺めると、一天にわかに掻き曇り、何やら不気味な暗雲が漂う。
石燕は、ふと何かを感じたようにあらぬほうを見つめた。
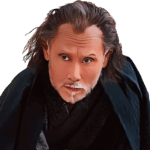 鳥山 石燕
鳥山 石燕何者じゃ?そなたは
薄暗い庭の木陰に、織を着た総髪の男が立っている。
次の瞬間、ピカーン、ドドーン!遠くで稲妻が凄まじい音を響かせた。
それから数日後のこと。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)これは…まことなのか?
定信は水野の報告書を読むなり、まるで雷に打たれたかのような衝撃を受けた。
大奥が殿には隠しておりましたものかと
こうしてはいられない。
慌ただしく登城し、中奥で家斉と差し向かいで話す。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)大奥の女中との間にお子をもうけられたそうで、おめでとうございます
大事なつとめを成しえ、安堵しておる
呆れたことに家斉は居直り、まるで反省の色がない。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)しかしながら、上様には仁政を為すため学を修めるつとめもまた、ございます。聞くところによりますと、大奥に入り浸り、栗山博士のご講義も不調にてお休みがちとのことで
定信の強い要請で幕府の儒官となった栗山は、家斉の侍講をしていた。
それぞれ秀でたことをすればよいと思うのじゃ。余は子づくりに秀でておるし、そなたは学問や政に秀でておる。それぞれつとめればそれでよいではないか
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)率先垂範(そっせんすいはん)
定信の口を衝いて出た言葉は、自らが人々の先頭に立って行動し、手本となることを意味する。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)武家は世の模範たるべしにございます。その武家の模範は上様にございましょう。女色に溺れ学問を放り出す。皆がそれを模範とすればいかなこととなるとお思いか!
硬骨の正論で厳しく諫められ、居直り将軍も屁理屈では太刀打ちできないのであった。
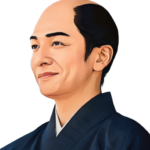 一橋 治済(家治のいとこ)
一橋 治済(家治のいとこ)突き詰めれば、政など誰でもできるもの。それこそ足軽上がりでもできたわけであるからの。しかし、後継をもうけることは上様にしかできぬ。ご立派だと思うがの
豪華な能の装束を身につけた治済は、息子同様に開き直った。
一橋邸に出向いた定信は早くも癇癪玉が破裂しそうになる。
しかしながら、上様は御台所となられる茂姫様との婚儀もいまだ。先に側室に子ができるなど、島津様はそれでよろしいのでございますか
演日は『鶏鵡小町』らしく、先ほどまで能役者に指導を受けていた重豪の衣装もまた電々しい。
まぁ、当家の出の御台様との間にも早々にお子をもうけてほしいが
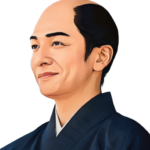 一橋 治済(家治のいとこ)
一橋 治済(家治のいとこ)此度はそのための稽古でもあったと上様も仰せであった
と治済。
それを聞いた重豪は、
さすが上様、お稽古熱心なことで!
と豪快に笑った。
定信のこめかみに太い青筋が立つ。
二人とも、まるで事の重大さを分かっていない。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)大奥は頼み事の温床となりまする。側室が欲をかけば島津様のお力にも響くことにもなりかねませぬぞ!
治済が面倒くさそうにため息をつく。
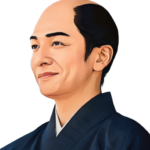 一橋 治済(家治のいとこ)
一橋 治済(家治のいとこ)そこはそなたが上手くやらねば。なんのための将軍補佐、奥勤めなのだ
まるで話にならない。
それにしても二人の衣装のきらびやかなことと言ったら・・・・・・。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)先ほどから気になっておるのですが、見事なご装束にございますな
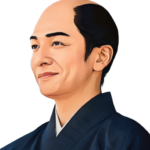 一橋 治済(家治のいとこ)
一橋 治済(家治のいとこ)じゃろう。近頃、改めて能に凝り出してな。能はそなたも好んでおったろう
そもそも能装束は高価なものだが、治済の美意識を反映したそれは桁違いだ。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)昔のことにございます。一橋様にも倹約をお願いしたかと存じますが
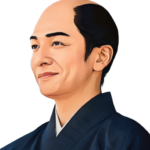 一橋 治済(家治のいとこ)
一橋 治済(家治のいとこ)案ずるな。一文も使っておらぬ。すべて島津がはからってくれた
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)賄賂も固く禁じましたことご存じにございましょう。一橋様がかようなことをなされては示しがつきませぬ!
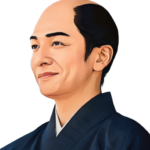 一橋 治済(家治のいとこ)
一橋 治済(家治のいとこ)困ったのう。ではひとつこれでよしなに
と定信に能面を差し出す。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)それがしを馬鹿にしておられるのか
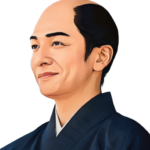 一橋 治済(家治のいとこ)
一橋 治済(家治のいとこ)いやいやわしはそなたから十万石ももろうたゆえ。せめて少しでも返そうかと思うたのじゃが
治済に見事にしてやられ、定信はぐうの音も出なかった。
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)遊里にて女郎、幇間などをお馬とした遊び、武芸の稽古と称したよし。商家の軒先にて主人の礼儀が気に食わず弓の稽古と暴れたよし。上から下まで、土風の廃退凄まじく。世の範たるべき徳川の侍がこの体たらくとは
定信が嘆くと、栗山は市中の報告書から顔を上げた。
たとえば上様には、各々立場に対する心得を書にしてお渡しになってはいかがにございましょう。そのほうが越中守様のお考えもしかと伝わりましょう
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)心得を作る
旗本や家人におきましては、まずは武よりは文に重きをおき、武家としての心得を叩き込むがよろしいかと
みな『論語』を読みだしておるとは聞いているのですが「格好だけで実のところ初歩の漢文すらろくに読めぬ者も多いと耳にいたしました。湯島聖堂で私が講釈などを始めましょうか
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)然様なことまでやっていただけるのでございますか?
お安い御用にございます。あぁ越中守様の文書も使いましょうか。確か、どこぞの若きご当主のために政のなんたるかをしたためられた。あれは実に分かりやすく書かれてございましたかと
 松平 定信(賢丸)
松平 定信(賢丸)『鵡言』のことにございますか?
家斉の教育だけでなく、このように栗山はこの先、定信の政治顧問として実際の施策に関わっていくことになる。
べらぼう35話のネタバレとあらすじを吹き出しで解説:新 歌麿
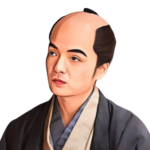 恋川 春町
恋川 春町直参のあいだでは、今、これを写すのが流行っておるのか
春町は『鸚鵡言』の写しを読みながら、隣を歩いている南敵に言った。
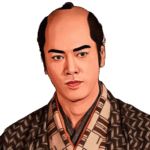 大田 南畝
大田 南畝ああ、ふんどし自らが記したものらしくてな。皆、せっせと書き写しておる
そこへ、「え!凧あげたら国が治まるのか!」「「鸚鵡言』にはそう書いてあると父上が仰せであった」という会話が聞こえてきた。見れば、手習所に通う武家の子弟たちだ。
春町は再び写しに目をやった。
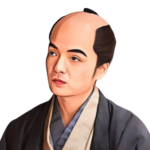 恋川 春町
恋川 春町紙鳶を上ぐるに外ならぬ、治国の術はもとあるを知るべし
という一節のことらしい。
蔦屋でも、まさに蔦重がていにその話をしていた。
 蔦重
蔦重どうもその一節が『凧を揚げると国が治まる』と誤解されてるらしいんだよ
 てい
ていまことにそうならよいですね。凧を揚げたら国が治まるなど、期らかで
 蔦重
蔦重確かになぁ!
想像しただけで楽しい。
文机に帳面を広げ、ウンウン唸りながら案思を考えていた蔦重は頬を緩ませた。
これを春町に教えたら、とびっきり面白いモンができるかもしれない。
そこへ、つよが顔を出した。
ちょいと旦那様、女将さん。んふ、歌先生がいらしたんだけどさ
やけにニヤニヤしていると思ったら、歌麿が見知らぬ女を連れている。
 てい
ていあの、そちらの方は
ていが尋ね、興味津々のつよはお茶を出しつつ、
いい人かい?そうだよね。それしかないよね!
とこらえきれずに先走る。
 蔦重
蔦重黙ってろババァ!
怒鳴りつけたものの、蔦重はいまだこの状況が把握できない。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)えっと、まず、石燕先生の話から、いいかい?
と歌麿。
 蔦重
蔦重先生、どうかしたのかい?
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)実はさ、石燕先生、亡くなったんだよ。先月の頭に
 蔦重
蔦重お前、なんですぐ知らせ寄越さねぇんだよ
つよも
そうだよ。水くさい!と涙声になる。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)急だったし、いろいろと後始末も多くて
ていが
 てい
てい病でも得られていたのですか?
と聞くと、歌麿はかぶりを振った。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)いや。年も年だったし、大往生だったと思いますよ。最後まで絵筆握りしめて、逝かれて
夕飯に呼びにいったら、絵を描いている途中で座ったまま亡くなっていたという。
歌麿は、石燕の遺作を蔦重に見せた。
色はついていないが、ほとんど描き終えてある。
それは、稲光と共に天を駆ける雷獣だった。
ふと蔦重の頭にエレキテルが浮かぶ。
 蔦重
蔦重雷を起こすあやかし・・・・・・
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)どうしたの?
と歌麿が怪訝な顔をする。
 蔦重
蔦重いや、なんとなく.....・このへんが源内先生っぽいなって
と顔の辺りを指す。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)まああやかしになってても不思議ではないお人ではあったよね
二人の話についていけないつよが、
あ、じゃあ、歌、こっち戻ってくる・・・・・
と言いかけ、歌麿が連れてきた女を見て
の、かい?
と語尾を濁す。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)そのことなんだけどさ、蔦重、俺、所帯を持とうと思って
 蔦重
蔦重ああ、所帯・・・・.所帯?
蔦重は顎が外れそうになったが、ていは
 てい
ていやはりそういうことにございますよね
と見当がついていた様子。
そもそも男女の機微に疎いうえ、蔦重の中の歌麿はまだ半分くらい、唐丸だった頃の小さな弟なのである。
若干気持ちがついていかないまま、蔦重は女のほうを見た。
目が合い、女がニッコリする。その表情に見覚えがあるような…。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)あ、おきよってんだ。ついでにおきよは聞こえないし、しゃべれないから
歌麿はさばさばした口調で言うが、ていとつよはどう反応していいものか分からない。
 蔦重
蔦重歌。あのよ、俺この人どっかで会ったことある気がすんだけど
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)そうだよ。お堂で、絵、拾ってくれた人だよ
 蔦重
蔦重あ!あぁ、あの時の!
きよが茶目っ気たっぷりにボコボコ殴る真似をする。
蔦重は思わず
 蔦重
蔦重お、おおお
と笑顔になった。
場の空気が和んだところで、歌麿が話を続ける。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)たまたま鉢合わせて、そこからおきよの絵描かせてもらうようになってさ。言葉がないから、おきよがなに考えてんのか、よく分からないんだけど
廃寺で初めてきよを描いてから、いろんなきよを数え切れぬほど描いた。
見ていると、きよは何かを思いながら、表情や仕草がくるくると変わる。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)顔つきや動きから、なに考えてんのか考えるのが楽しくて。それを絵にするのも楽しくて。時が経つのを忘れるってぇか
こんなに幸せそうにほほ笑む歌麿を、蔦重は見たことがない。
すると、歌麿が居住まいを正して言った。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)蔦重、俺、ちゃんとしてぇんだ
 蔦重
蔦重ちゃんと・・・・・?
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)ちゃんと名をあげて、金も稼いで、おきよにいいもん着させて、いいもん食わせて、ちゃんと幸せにしてぇんだ
 蔦重
蔦重・・・・・・・おう
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)で、石燕先生が借りてた仕事場をそのまま借りられねぇかと思ってさ。手持ちだけじゃちょいと足りねぇもんで。これ、買い取ってもらえねえかな
と風呂敷に包んであった絵を差し出す。
丸めた絵が全部で十二枚ほどある。
その中の一枚を広げたとたん、蔦重は絶句した。
 蔦重
蔦重お前、これ
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)うん。まえに描けなかった『笑い絵』さ
笑い絵、つまり春画である。
蔦重はごくりと息を呑み、絵を一枚一枚見ていった。
ていとつよも順に見ていく。
三人とも声が出ない。
いや、呼吸すら忘れている。
その表情は、ただならぬものを見ている者のそれだ。
 蔦重
蔦重.......よく、描けたな
すべて見終わったあと、蔦重は止まっていた息を吐くように言った。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)おきよのおかげなんだよ。おきよがいたから、幸せって何かって分かって。そしたら、幸せじゃなかったことも絵にすることができた
蔦重がじっと黙り込んでいるので、歌麿は気に入らなかったのかと勘違いした。
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)ダメかい?通しで見ると実はまったくまとまりねぇんだよな
蔦重は改めてきよに向き直り、いきなりガバッと頭を下げた。
 蔦重
蔦重おきよさん、ありがた山にごぜえます! こいつにこんな絵を描かせてくれてありがた山です!
新しい歌麿だ。
絵師としての真の歌麿の誕生だ。
歌麿は、きよとの出会いで忌まわしい過去を乗り越えたのだ。
きよの戸惑いに気づかず、蔦重は頭を下げたまま興奮して続けた。
 蔦重
蔦重こりゃ間違えなく、こいつを当代一に押し上げる。この世でほかの誰にも描けねぇ、こいつしか描けねぇ絵です!どうか、一生こいつのそばにいてやってくだせぇ!
 歌麿(唐丸)
歌麿(唐丸)蔦重、俺は嬉しいんだけどさ
と歌麿。
つよが
おきよさんにはまったく伝わってないと思うよ
と教える。
蔦重が慌てて顔を上げると、きよは不安そうに歌麿の袖を摑んでいる。
たぶん、身を引いてくれとでも頼まれたって思ってんじゃないかな
歌麿に苦笑いされ、蔦重は己の鈍感さに愛想が尽きた。
べらぼう35話のネタバレとあらすじを吹き出しで解説:幸せな蔦重
その夜、蔦重は一人で祝い酒を飲んだ。
ていは歌麿の笑い絵を飽きず眺めている。
 蔦重
蔦重なんだい。おていさん、実は笑い絵好きなのかい?
 てい
てい歌さんの絵なら虫の絵のほうがよほど好きです。でも、ここに歌さんの心血が注がれているのは感じます
あえて答えなかったが、蔦重も同じ思いだった。
 てい
ていならば、ちゃんと見なければ、と。私は蔦屋の『女将』にございますので
 蔦重
蔦重・・・・・出会った頃のあいつは、ただただ死ぬのを待ってるってなふうだったんだよ。生きる欲みてえなのがこれっぽっちもなくて。・・・・そんなあいつがさ、『ちゃんとしてえ』ですよ。『ちゃんとしてぇ』って言ったんですよ。俺やもう嬉しくてさ・・・・・
ていが、空になった蔦重のぐい呑みに酒を注いでくれる。
 てい
ていではこちらもちゃんと仕立て、ちゃんと売らねばなりませんね。ちゃんと取り戻せますように。歌さんにお支払いした『百両』を!
 蔦重
蔦重今、金の話しなくてもいいんじゃねぇですかい?
たちまち逃げ腰になる蔦重。
 てい
てい私は蔦屋の『女将」にございますので
そうであった。
蔦屋の女将は、こと金に関しては駿河屋の親父なみに容赦ない。
でもまあ、歌麿ときよがあの金で仕事場を借りることができ、古着の着物なんかを買い集めて、楽しそうに浮かれて選び合いっこしている様子を思い浮かべると、ただもう幸せな蔦重であった。
べらぼう35話のネタバレとあらすじを吹き出しで解説:おていの心配
蝉の鳴き声がいつしか消え、雷が声を収める秋の半ば、いよいよ春町の草稿が上がってきた。
蔦重と南畝、喜三二、政演、三和、ていも加わって原稿を回し読みする。
 蔦重
蔦重このしまい方は傑作ですね!
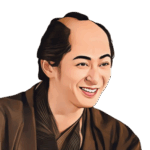 北尾 政演
北尾 政演なぁ!鸚鵡の言葉?『秦吉了(九官鳥)の言葉』を勘違いした奴らが皆で揚げたら鳳凰が勘違いして出てきちまって、なんだか天下太平の世になっちまうってなぁ
大絶賛の政演と三和、喜三二も
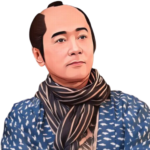 朋誠堂 喜三二 (平沢)
朋誠堂 喜三二 (平沢)どうだろう、まぁ!
という口癖がいかにも楽しげで、春町もほかの面々も大笑いする。
文句のつけようのない草稿であった。
蔦重が
 蔦重
蔦重じゃまぁ、これで仕上げに進めますか
と締めようとした時、
 てい
ていお待ちくださいませ
と、ていから制止の声がかかった。
 てい
ていこれはさすがにからかいがすぎるのではないでしょうか。お武家様たちのひどい振る舞い、これでは文武などいくら勧めたところで無駄だと言わんばかりです
 蔦重
蔦重けどまあ、これに近いことは現にも起こってるわけでさ
 てい
ていだからこそまずいかと
 蔦重
蔦重いいじゃない。最後は兎にも角にも皆で凧揚げてめでたしめでたしなんだから!
 てい
ていそこもあまりにもおふざけがすぎますかと!
 蔦重
蔦重だいたいそうなりや朗らかでいいってたの、女将さんでしょうが!
過熱する本屋夫婦の言い争いに、
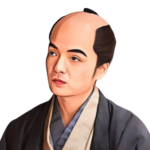 恋川 春町
恋川 春町俺はさしてふざけておるつもりはないのだ
と作者の春町が入ってきた。
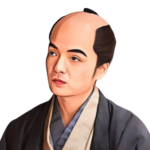 恋川 春町
恋川 春町ふんどしの思い描いたとおり世は動かぬかもしれぬ。だが、思うようには動かぬ者が思わぬ働きを見せるかもしれぬ。ゆえに躍起になって己の思うとおりにせずともよいのではないか、少し肩の力を抜いてはいかがか、と。俺としてはそういう思いも込めて描いたものだ
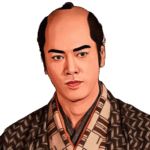 大田 南畝
大田 南畝からかいではなく、諫めたいというところか
と南畝。
しかし、ていは納得しない。
 てい
ていそれはからかいよりもさらに不遜、無礼と受け取られませんでしょうか
と懸念を募らせる。
真面目さはていの長所だが、商売にいちゃもんをつけられたようで蔦重は露骨に眉をひそめた。
 蔦重
蔦重んなこと言いだしたら、そもそも不遜で無礼なことをやろうって話なわけでさ
 てい
ていとにかく私は、これは出せば危ないと存じます
再び押し問答が始まろうとした時、次郎兵衛がつよと話しながら座敷に入ってきた。
 蔦重
蔦重どうしたんです?義兄さん
 次郎兵衛(蔦重の義理の兄)
次郎兵衛(蔦重の義理の兄)ちょいと面白え話を小耳に挟んでさ。こりや早くお前に知らせなきゃって。どうもよ、越中守様ってなぁ、大の黄表紙好きらしいぜ
驚きの新事実である。蔦重は俄然、勢いづいた。
 蔦重
蔦重それ、まことなんですか?
 次郎兵衛(蔦重の義理の兄)
次郎兵衛(蔦重の義理の兄)まえにお屋敷で奉公してた人から聞いたから間違いねぇよ。金々先生以来の恋川春町贔屓、蔦屋のことも大の贔屓だって話だぜ
そうとくれば話は大違いし。
一同は、誰からともなくニンマリと目配せし合った。
べらぼう35話のネタバレとあらすじを吹き出しで解説:凧と運命の糸
蔦車たちが本作りに着手する一方、定信は栗山の助言を受け、各種『心得」を作っていた。
上様のお心に留めていただきたき事を私自らしたためましてございます。ぜひ、ご一読を!
家斉には「魚心得条』を、老中たちには「老中心得」を。
定信運身の出来栄えであった。
たくさんの凧が雲一つない初空で遊んでいる。
子どもたちや親子連れがあちこちで凧揚げを楽しんでいる頃、開店準備に忙しい蔦屋では、恋川春町作「鶏鵡返文武二道』、唐来三和作「天下一面鏡梅鉢』などの黄表紙、そして歌麿の錦絵が店頭に並べられた。
蔦重がふと『鶏鵡返文武二道』を開いた時、どこかでプツリと一枚の凧が落ちた。
天明改まり寛政元(一七八九)年。それは、蔦屋の運命の分かれ目となる年であった。
べらぼう次回放送
次回のべらぼうネタバレ第36話はこちら

べらぼうのネタバレとあらすじ:一覧
2025年9月

【べらぼう 9月】あらすじ一覧
第34話 9/7(日) ありがた山とかたじけ茄子
第35話 9/14(日)間違凧文武二道
第36話 9/21(日) 鸚鵡のけりは鴨
第37話 9/28(日) 地獄に京伝
べらぼう35話:筆者の見解
 見返りさん
見返りさん放送後に記載いたします~!
↓↓↓


